仕事から帰ってきて
夕食の準備もままならないまま
疲れ切った体で
子どもをお風呂に入れようとしたら
「ヤダ!」と泣き叫ばれてしまう…
そんな状況に
心が折れそうになっていませんか?
「今日も一日頑張ったのに
どうして思い通りにいかないんだろう」と
落ち込む気持ち
すごくよく分かります。
共働きで毎日時間に追われているからこそ
子どもと向き合う貴重な時間くらいは
笑顔で過ごしたいですよね。
でも現実はなかなか厳しくて
お風呂の時間ひとつとっても毎日のように
バトルが勃発しているご家庭は多いはず。
実際 多くの共働き家庭が
「子育ての悩み」として
子どものお風呂嫌いを挙げています。
子育て情報サイト『ママリ』が
2022年に行ったアンケート調査によると
「子育てで最も大変なことは?」
という問いに対し
「お風呂や着替え」と回答した親が
全体の約20%にものぼりました。
これは 食事や寝かしつけと並んで
多くのパパ・ママが直面する
共通の課題と言えます。
実は 子どもがお風呂を嫌がるのには
月齢ごとの成長段階に合わせた
理由があります。
「うちの子はなんでお風呂が嫌なんだろう?」
「どうすれば楽しく入ってくれるようになるの?」
そんな疑問を抱えているあなたに
このサイトでは 0歳から3歳までの
子どもの発達段階に合わせた具体的な対策と
先輩パパ・ママのリアルな声
そして共働き家庭の強い味方となる
時短グッズまで
ぎゅっと凝縮してご紹介します。
この記事を読み終える頃には
お風呂の時間が「大変な義務」から
「子どもとの大切なふれあいタイム」に
変わるヒントが見つかるはず。
ぜひ最後まで読んで
今日からできることを試してみてください。
忙しい夜でも“お風呂チェア”があれば
安全・快適に入浴できます。
「もう疲れた…」共働き夫婦がお風呂で直面する3つの壁
子どもが突然お風呂を嫌がるようになると
「何か原因があるのかな?」と
心配になりますよね。
でも その理由を知ることで
子どもの気持ちに寄り添った対応が
できるようになります。
共働き家庭では
時間や心の余裕がない中で
なぜ子どもがお風呂を嫌がるのか
その根本的な理由を理解することが大切です。
ここでは 0〜3歳児が共通して抱える
お風呂への抵抗感と
共働き家庭ならではの特殊な状況について
詳しく見ていきましょう。
子どもの「イヤ!」には
実はちゃんとした理由が
あることを知るだけでも
親の気持ちは少し楽になります。
なぜうちの子だけ?お風呂嫌いに隠された月齢ごとのサイン
子どもがお風呂を嫌がるのには
いくつかの一般的な理由があります。
まず 最も多いのが・・・
まず 最も多いのが「単なる気分」です。
特にイヤイヤ期の子どもは
自分の気持ちがうまく表現できず
お風呂に入るという親の指示に抵抗することで
自己主張をしようとします。
次に多いのは不快感
次に「熱い・冷たいなどの不快感」です。
大人にとっては適温でも
子どもにとっては熱すぎたり
浴室が寒かったりすることがあります。
または怖さ
また「お風呂が怖い」と感じる子もいます。
シャワーの音や 湯船に浸かった時の水圧
体の浮く感覚などが苦手な場合もあるのです。
そして・・・
そして 「遊びを中断されるのが嫌」
というのも大きな理由です。
お風呂は
楽しい遊びの最中にやってくる
「強制終了」のように
感じられるのかもしれません。
これらの理由を理解することで
無理やり入れようとせず
子どもの気持ちを尊重した
アプローチが可能になります。
例えば
イヤイヤ期の子どもが「お風呂ヤダ!」
と叫んだとしても
それは「お風呂が嫌い」なのではなく
「今やっている遊びを続けたい」という
気持ちの表れかもしれません。
その場合
「お風呂に入ったら
お風呂のおもちゃで遊ぼうね」
と誘うことで
気持ちを切り替えさせることが
期待できます。
また 水温や浴室の温度を再確認し
不快な要素を取り除くことも効果的です。
特に冬場は 脱衣所を事前に
暖めておくなどの工夫が役立ちます。
時間との戦い!共働きならではのお風呂タイム どう乗り越える?
共働き家庭では 時間との戦いが日々の
大きなテーマですよね。
仕事から帰宅して 夕食の準備
子どもの世話 そしてお風呂…と
怒涛のスケジュールをこなす中で
お風呂に手間取ってしまうと
その後の時間が全てズレてしまいます。
特に「早くしないと!」という焦りは
子どもにも伝わってしまい
結果としてお風呂嫌いを
助長させてしまうことがあります。
この時間的なプレッシャーこそが
共働き家庭ならではの
課題と言えるでしょう。
この問題に対処するためには
完璧主義を少し手放し
「効率化」と「リラックス」を
両立させることが重要です。
まずは準備
まず お風呂の準備を
事前に済ませておくことが挙げられます。
お風呂のおもちゃや着替えを
脱衣所に用意しておくことで
スムーズに入浴を開始できます。
次に分担
次に 夫婦で役割分担を
明確にすることも効果的です。
片方が子どもと入浴している間に
もう片方が
夕食の仕上げや片付けをするなど
お互いの負担を減らす工夫が大切です。
例えば 週末に時間のある時に
お風呂で使えるおもちゃを
いくつか用意しておき
平日はその中から
好きなものを選ばせるようにすると
子ども自身がお風呂を楽しみにする
きっかけになります。
また お風呂に入れた日は
「今日はよく頑張ったね!」と
たくさん褒めてあげることで
子どもも達成感を感じ
次への意欲につながることが期待できます。
こうした小さな工夫が
日々のストレスを減らし
お風呂の時間を親子で
笑顔で過ごすための第一歩になるでしょう。
0〜3歳児の「お風呂イヤイヤ」を「楽しい!」に変える月齢別アイデア
子どもがお風呂を嫌がる理由を
理解したところで
いよいよ具体的な対策です。
子どもの発達はめまぐるしく
昨日まで通用した方法が
今日は通用しないこともありますよね。
だからこそ
その時々の月齢や成長段階に合わせた
アプローチが欠かせません。
こちらでは 0〜3歳までの子どもの
「今」に寄り添った解決策を
共働き家庭でも無理なく実践できる
具体的な方法とともにお伝えします。
お風呂タイムを親子の笑顔あふれる時間に
変えるためのヒントが
きっと見つかるはずです。
0〜6ヶ月|ベビーバス卒業の不安を解消する第一歩
生後6ヶ月頃になると
ベビーバスを卒業して
大人と一緒の湯船に入る機会が増えます。
この時期に嫌がる理由の一つは
ベビーバスと比べて湯船が
広くて深いことへの不安感です。
子どもの安心感を確保するためには
親がしっかりと支え
優しく声をかけながら入ることが大切です。
また 手足をバタバタさせる
「遊び」として捉えさせることで
水への恐怖心を減らすことができます。
赤ちゃんの不安を
やさしく支える定番アイテム。
体験談 パパ・Kさん、34歳、生後5ヶ月
うちの子は大人用のお風呂に慣れなくて
泣いていたんですが
お風呂用の浮き輪を試したら
ぷかぷか浮くのが楽しいみたいで
笑顔になってくれました。
最初は自分がしっかり支えなきゃと
力んでいましたが
浮き輪のおかげで子どもの体が安定し
お互いリラックスして
入れるようになりました。
体験談 ママ・Sさん、32歳、生後7ヶ月
最初はベビーバスを湯船に浮かべて
徐々に広さに慣れさせました。
その後 湯船の中で歌を歌ったり
お風呂用のおもちゃで遊んだりするうちに
自分から
お風呂に入るようになりました。
お風呂嫌いだったのが嘘みたいに
今ではお湯をばしゃばしゃ叩いて
楽しんでいます。
7ヶ月〜1歳|好奇心と飽きっぽさに寄り添う遊びの提案
この時期は ハイハイや
伝い歩きができるようになり
行動範囲が広がります。
好奇心旺盛な時期だからこそ
マンネリ化したお風呂に
飽きてしまうことがあります。
お風呂の時間を
遊びの延長として捉え
湯船で遊べる新しいおもちゃや
泡風呂入浴剤など
五感を刺激するアイテムを導入すると効果的です。
滑りやすい時期でも安心。
ママ・パパの負担を減らす便利アイテム!
体験談 ママ・Mさん、36歳、1歳2ヶ月
娘が急にお風呂を嫌がるようになった時
お風呂用の知育ポスターを
貼ってみました。
ひらがなや動物の絵を見て
「これなあに?」と話しかけているうちに
いつの間にか湯船に
浸かってくれるようになりました。
毎日同じ内容で飽きないように
一週間ごとに
ポスターを貼り替えるなどの
工夫もしています。
体験談 パパ・Tさん、38歳、1歳6ヶ月
週末だけ僕が一人で
子どもをお風呂に入れています。
その時は好きなキャラクターの
シャンプーボトルを使ったり
普段使わないような
新しいおもちゃを出したりして
スペシャル感を演出しています。
普段は早く済ませたいと
思ってしまいますが
週末だけは僕も一緒に
遊びながら入るようにしています。
1~3歳|イヤイヤ期を乗り越える!「自分でやりたい」を叶える魔法
1歳半頃から始まる「イヤイヤ期」は
お風呂でも発揮されやすい時期です。
「自分でやりたい!」という
自立心が芽生える一方で
親の言うことを聞かないという
葛藤も生まれます。
この時期には 子ども自身に
選択権を与えることが重要です。
遊びながらシャワーで笑顔に!
子どもが自分から入りたくなる工夫。
体験談 ママ・Aさん、35歳、2歳
お風呂に入りたがらない息子に
「ゾウさんとワニさん
どっちと一緒にお風呂に入る?」と
聞くようにしました。
自分で選んだおもちゃと
一緒に入れるのが嬉しかったみたいで
すんなり入ってくれるようになりました。
選ぶおもちゃを限定することで
遊びすぎを防止し
時短にも繋がっています。
体験談 パパ・Yさん、39歳、2歳半
娘が「ママと一緒じゃなきゃヤダ!」
と泣き出した時
娘が私を洗ってくれる
「パパ洗いっこゲーム」を
提案しました。
娘が泡をつけてくれるのを
「気持ちいいね〜」と褒めると
大喜びで 自分から体を
洗ってくれるように!
娘が楽しんでくれるので
今では僕から
「今日はパパを洗ってくれる?」
と誘うこともあります。
忙しい日のお助けアイテム!お風呂の負担を減らす便利グッズ
子どもがお風呂を嫌がる理由や
月齢別の対策法を試しても
日々の忙しさの中では
なかなかうまくいかないこともありますよね。
共働き家庭にとって
時間と心の余裕を確保することは
何よりも大切です。
そこで頼りになるのが
お風呂の時間をグッと楽にしてくれる
便利グッズです。
今回は 子どものお風呂嫌いを克服する
きっかけになるアイテムから
パパやママの負担を減らす
時短グッズまで 厳選してご紹介します。
子どもが夢中になる!お風呂が楽しくなるおもちゃ&ツール
子どもがお風呂を嫌がる原因の一つに
単純に「つまらない」と
感じていることがあります。
そんな時 お風呂の時間を
遊びの場に変えるアイテムが効果的です。
例えば
水で描けるお風呂用のお絵かきシートや
光るおもちゃ
カラフルなバスボムなどは
子どもの好奇心を刺激し
「お風呂に入りたい!」という気持ちを
引き出すきっかけになるかもしれません。
これらのアイテムは
お風呂場をいつもと違う
特別な空間にしてくれるので
子どもの抵抗感を減らすことが期待できます。
ただし おもちゃの素材や
安全性には注意して
対象年齢に合ったものを選びましょう。
月齢別|お風呂イヤイヤ対策早見表
| 月齢 | おすすめ対策アイテム | |
|---|---|---|
| 0〜6ヶ月 泣いて入れにくい時期 |
 |
着替えの準備から体洗い スキンケアまで これ1つでOK |
| 6〜12ヶ月 動きが活発で滑りやすい |
 |
吸盤付き 滑り止め防止のバスマットで活発な赤ちゃんでも安心 |
| 1〜2歳 遊びたい気持ちが強い |
 |
吸盤付きで遊び方は無限大 |
| 2〜3歳 「自分でやりたい」期 |
 |
自分でやりた時期にぴったりのふんわりスポンジで 一緒に体を洗いましょう。 ふんわりスポンジの子供も使えるボディブラシ |
| 3歳以上 入浴を嫌がる |
 |
どうしたら進む?鼻からお湯がぴゅー!次は順番ね など 語彙力やマナーを学びながらお風呂が楽しい場所に。 BATH TOYお風呂のおもちゃ |
時短を叶える!パパママの負担を減らす心強い味方
共働き家庭にとって
お風呂の時間をいかに短縮できるかは
重要な課題です。
手間を省くことで
心に余裕が生まれます。
たとえば
シャンプーと全身洗浄料が一緒になった
オールインワンタイプの商品は
泡立てや洗い流しの
手間が省けて便利です。
また
浴室の床を掃除するロボットや
お湯の温度を自動で一定に保つ機能なども
家事の負担を減らすのに役立ちます。
さらに 忙しい日には
ベビーシッターや
家事代行サービスを利用して
お風呂の時間だけプロに任せる
という選択肢もあります。
これらのサービスを活用することで
パパやママの心身の疲労を軽減し
家族全員が笑顔でいられる時間を
増やすことができるでしょう。
FAQ 回答
子供とのお風呂に関する疑問を
まとめてみたので
ぜひ参考にしてみて下さい。
子どもがお風呂にハマる!おすすめアイテムは?
お風呂に対する
子どもの抵抗感を和らげるには
遊びの要素を取り入れるのが
効果的です。
水に浮くアヒルや魚 水鉄砲など
単純な動きで楽しめるおもちゃが定番です。
特に 壁に貼れるタイプの知育おもちゃは
水に濡らすとくっつく性質を利用して
パズルや文字遊びができます。
また 泡風呂入浴剤やクレヨンなど
五感を刺激するアイテムもおすすめです。
ただし おもちゃを複数用意すると
選択肢が増えて
逆に混乱することもあるため
最初は2〜3個に絞って
子どもの興味に合わせて
入れ替えていくのがいいでしょう。
ワンオペに限界…夫婦で協力するヒントは?
まずは 具体的に何を手伝ってほしいかを
伝えることから始めましょう。
「お風呂に入れてくれると
夕食の準備が進むから助かるな」など
感謝の気持ちを交えながらお願いすると
相手も快く応じてくれる可能性が高まります。
また 育児のタスクを「見える化」するのも
一つの手です。
たとえば 一日のスケジュールを書き出して
お風呂の時間がどれだけ大変かを
共有することで
相手も状況を理解しやすくなります。
お互いの状況を尊重し
対話を通して協力体制を築いていくことが
大切です。
なんで家だけ嫌がるの?保育園との違いって?
保育園や幼稚園では
集団行動の一環として
お風呂やプールに入る時間が
決まっています。
周りの子どもたちが
楽しそうにしている姿を見て安心したり
保育士さんという
「権威ある人」の指示に従うことで
すんなり入ることが多いようです。
一方 家では親と一対一の環境になり
甘えが出たり
自分のペースで動きたいという気持ちが
強く出たりします。
また 保育園での疲れが原因で
家ではリラックスしたいと思っていることも
考えられます。
家でも集団での遊びのような楽しさや
ルールを設けることで
子どもが安心して入れるようになるかもしれません。
「まだ遊びたい!」お風呂から出ない子への対処法は?
お風呂の時間が楽しくなると
今度は「出たくない!」という
新たな問題に直面することがあります。
これは お風呂を楽しい遊び場だと
認識してくれた証拠。
まずは
「あと5回泡を流したらおしまいだよ」など
終わりの目安を具体的に伝えることで
心の準備を促しましょう。
また「お風呂が終わったら
楽しい絵本を読もうね」など
お風呂後の楽しみを提示するのも効果的です。
お風呂の終わりをスムーズにする工夫も
親子のストレス軽減につながります。
まとめ
共働き家庭にとって
子どもと向き合う時間は貴重であり
お風呂の時間が
ストレスになってしまうのは辛いですよね。
しかし この記事でご紹介したように
子どもがお風呂を嫌がるのには
月齢に応じた理由があり
それに合わせた工夫で
解決できる可能性があります。
遊びの要素を取り入れたり
便利な時短グッズを活用したり
そして何よりも
「完璧じゃなくて大丈夫」という
気持ちを持つことが大切です。
パパやママが笑顔でいられることが
結果として子どもの笑顔にもつながります。
「お風呂を楽しくする」という視点で
もう一度今日からのお風呂タイムを
見つめ直してみませんか?
この小さな変化が
あなたの家庭の毎日をきっともっと
明るくしてくれるはずです。
参考文献・引用元リスト
ママリ 2022年 子育てに関するアンケート調査
厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」(2019年改訂版)

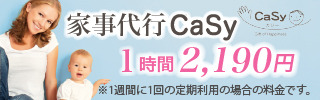


コメント