仕事を終えてから
寒い夜に2人の子どもを
順番にお風呂に入れる…。
経験のある方ならわかると思いますが
想像以上に大変なミッションです。
赤ちゃんはすぐ湯冷めするし
上の子は「早く入りたい!」と待ちきれない。
自分の髪や体をゆっくりケアする
時間なんてなくて
気づけば濡れたまま寝かしつけ…。
そんな毎日を繰り返していると
「これって私だけ?」
「他の家庭はどうしてるの?」
と不安になることもありますよね。
私も同じように悩んでいたので
その気持ち すごくわかります。
でも安心してください。
同じ状況で試行錯誤している
ママ・パパはたくさんいます。
この記事では
私自身の体験や先輩パパママの工夫
さらに便利なアイテムを交えて
冬のワンオペお風呂を
少しでもラクにする方法をまとめました。
「完璧じゃなくてもいい」
「ちょっと工夫するだけで変わる」
そんな気持ちで
読んでいただけたら嬉しいです。
冬のワンオペお風呂はなぜ大変?
夏と違って冬のお風呂が大変なのは
ただ寒いからではありません。
脱衣所が冷える
赤ちゃんも上の子も湯冷めしやすい
待ち時間に上の子が走り回って
捕まえるのもひと苦労
浴室内では転倒や溺れの心配もある
これらが一度に押し寄せるので
心身ともに疲れやすいのです。
私も「今日はやめちゃおうかな…」と
何度思ったかわかりません。
でも 整理してみると 意外と
改善できるポイントも見えてきます。
寒さ対策や動線の工夫
便利グッズの活用など
小さな準備で
ずいぶんラクになる瞬間は確かにあります。
ワンオペで2人を入れる前の準備が成功のカギ
冬のお風呂で一番大切なのは
とにかく段取り。
入る前に準備をしておくかどうかで
その後の慌ただしさがまるで違います。
脱衣所の寒さ対策(ヒーター・浴室暖房)
我が家では 小型ヒーターを使って
あらかじめ脱衣所を温めています。
これをやるだけで
子どもたちが震えることが減り
気持ちに余裕が生まれました。
タオルや着替えのスタンバイ術
赤ちゃんは湯冷めしやすいので
大判のバスタオルやバスローブを
広げて準備。
出た瞬間に包めると安心です。
上の子・下の子・自分
それぞれの着替えをカゴごとに
分けて置いておくと
探す手間もなくスムーズ。
私はきれいに畳むのではなく
少し崩して重ねておきます。
そうすると1枚ずつ
スッと取れるので意外と便利なんです。
保湿ケアも忘れずに。
体を拭いたあと
最初に使う保湿剤は
すぐ手に取れる所に置けるといいですね。
2人同時入浴の流れと順番のコツ
いよいよ本番。
ここはルーティン化すると
かなりラクになります。
我が家の流れはこんな感じ👇
脱衣所で準備完了
3人でシャワーを浴びて
体を温める
上の子を浴槽に入れて
おもちゃで遊ばせる
赤ちゃんを洗って
ベビーチェアやマットで待機
自分をサッと洗う
上の子を洗う
(できる部分は自分で)
3人で湯船タイム
赤ちゃんを先に上げてタオルで包む
上の子を上げてすぐ保温
保湿&着替え
兄弟(姉妹)の性格や気分によっては
順番を逆にしたり
ルールを「今日は◯◯くんが先」など
柔軟に変えたりするのもありです。
我が家では「次は◯◯の番だよ」と
声をかけるだけで
グズリが減ったこともありました。
赤ちゃんを先に洗うメリット
基本的には赤ちゃんを
先に洗ってあげます。
赤ちゃんは小さい分
体力も少なく 湯冷めもしやすいため
先に洗って
体を充分に温めてから
ベビーバスマットや
ベビーチェアで待機させることで
負担を減らすことができます。
上の子を待たせる工夫(おもちゃ・マット)
上の子を浴槽で待たせるときは
まず安全が第一ですよね
私は浴槽内でも使える
滑り止めマットを使用していました。
遊ぶおもちゃは
お風呂でしか遊べないものや
繰り返し何度も
遊びたくなるような物を
選んでいました。
上の子の機嫌が
あまりよくない時は
「今日はシャボン玉しちゃおうか!」
と特別感を演出したりも
していました。
ママ・パパの体を洗うタイミング
ワンオペお風呂の
ママ・パパが体を洗うベストタイミングは
赤ちゃんを洗い待機させたあと。
上の子が飽きずに
遊んでくれているこの間に
ササっと体を洗い
洗髪まで済ませます。
この時に
泡ボディソープや
リンスインシャンプーを使うと
さらに時短になりますよ。
お風呂上がりから寝かしつけまでのルーティン
みんなで温まったあとは
溺れるリスクを減らすため
上の子を浴槽から出し
まずは赤ちゃんを連れて脱衣所へ移動。
ママはバスタオルを羽織って
湯冷めを防ぎながら
赤ちゃんの着替えと保湿を行います。
ポンプ式のローションなら
片手でも使えて
抱っこしながらでも塗りやすいです。
最後に上の子を浴室から出して
同じように
着替えと保湿を済ませます。
上の子には「自分で塗ってみようか」
と声かけをすることで
自立心を育てつつ
ママが自身の保湿をする
時間にもなります。
赤ちゃん・上の子→寝かしつけ
全てが終わったら最後は寝かしつけ。
冬は体が温まっているので
チャンスです。
赤ちゃんは
着替え後すぐ授乳すると
リラックスして寝やすいです。
その間 上の子には
絵本や静かにできる遊びを提案すると
落ち着いて待ってくれます。
授乳が終わったら赤ちゃんを寝かせ
次に上の子の寝かしつけへ。
「お風呂→絵本→おやすみ」
という流れを毎日同じにすると
自然とリズムが整いやすくなります。
私自身も
「この時間はクールダウン」
と思うようにして
できるだけ焦らず過ごすようにしています。
先輩ママ・パパが実践した冬のワンオペ風呂アイデア
「毎日が戦場」「お風呂が一番の難所」
そんな声が多い冬のワンオペ入浴。
実際に工夫して乗り切った声は
とても参考になります。
こちらでは 実際に
2人育児を経験した方々の
リアルなエピソードを紹介します。
脱衣所の寒さ対策の工夫(ママ/3歳&0歳)
冬の脱衣所が寒すぎて
次女が泣き出すのが悩みだった
というママさん。
小型の温風ヒーターを導入し
入浴前から脱衣所を
暖めるようにしたところ 泣きが激減。
さらに
親子で使えるバスローブを用意し
出た瞬間に包めるようにしたことで
湯冷めも防げたそうです。
「自分も冷えないから
着替えも余裕ができた」
とのことでした。
お風呂後の泣き対策(ママ/2歳&0歳)
お風呂上がりに次男が泣き止まず
長男も不機嫌になるのが
悩みだった東北在住のママさん。
脱衣所にお気に入りのガーゼと
メリー(音が鳴るおもちゃ)を
設置したところ
次男が落ち着いて待てるように。
長男には
「今手が離せないから
ママの体拭いてくれる?」
とお願いすると
頼られた嬉しさからか
喜んで協力してくれるように
なったそうです。
順番ルールで兄弟げんかを防ぐ(パパ/2歳&0歳)
2歳と0歳の兄弟を
同時に入浴させていたパパさんは
毎回どちらを先に洗うかで
揉めていたそう。
そこで
「今日は○○くん 明日は○○ちゃん」と
順番ルールを導入。
事前に伝えておくことで
子どもたちも納得して待てるようになり
入浴がスムーズに。
「ルールがあるだけで子どもも安心する」と
実感したそうです。
テレビや音楽の活用例(ママ/3歳&1歳)
お風呂後の着替えや寝かしつけが
バタバタしていたママさんは
NHKの幼児向け番組を活用。
次男には授乳
長男にはテレビを見せながら
着替えさせることで
ママの負担が大幅に軽減。
「寝る前にテレビはダメと思ってたけど
使い方次第で味方になる」
と感じたそうです。
冬のワンオペお風呂を助ける便利グッズ
正直 グッズの力は偉大です。
バスチェアやお風呂マット
ベビー用バスローブなどは
あるとないとで大違い。
安全面や時短効果を考えると
使えるものは
どんどん取り入れていいと思います。
赤ちゃん向けアイテム
| 商品名 | 特徴 | 参考価格 | 詳しくはこちら | |
 |
リッチェル ひんやりしない お風呂マット |
新生児から使用可能 |
3160円 |
ひんやりしない お風呂マットを 見てみる |
 |
クラウン ベビーバス |
新生児から使用可能 高い背面ガードで安定感がある シンクや洗面台でも使用可能 |
3480円 | クラウン ベビーバスを 見てみる |
 |
Aprica バスチェア |
新生児から使用可能 リクライニング付きで 成長段階に合わせて使える |
3930円 | Aprica バスチェアを 見てみる |
 |
マカロンバス | 0歳から使用可能 浴槽と同じ機能で冬に最適 待機場所として兄弟で使用可能 |
3520円 | マカロンバスを 見てみる |
上の子が喜ぶアイテム
| 商品名 | 特徴 | 参考価格 | 詳しくはこちら | |
 |
くまポン |
ベビーキッズ用バスローブ |
2480円 |
くまポンを見てみる |
 |
ノンスリップ バスマット |
浴槽・浴室に取り付け可能 |
1980円 |
ノンスリップバスマットを 見てみる |
 |
組み立て式 レールおもちゃ |
吸盤付きで 浴槽や浴室に設置可能 ピタゴラ要素で子供が夢中 レールの配置換えが自由自在 |
5299円 | 組み立て式レールおもちゃ を見てみる |
 |
くっつき虫 |
誤飲チェッカー確認済で安全 |
2980円 |
くっつき虫を見てみる |
ママ・パパの時短グッズ
| 商品名 | 特徴 | 参考価格 | 詳しくはこちら | |
 |
マー&ミー Latte リンスイン シャンプー |
家族全員で使用可能 |
730円 |
マー&ミー Latte リンスインシャンプーを見てみる |
 |
ふんわりバスローブ |
全身の水分をしっかり吸収 |
3500円 |
ふんわりバスローブを 見てみる |
 |
BABY BORN Face&Body Milk |
家族全員で使用可能 べたつき・白残り無し 顔・全身に使えて大容量 1本で保湿完了 |
4180円 | BABY BORNFace&Body Milkを見てみる |
FAQ回答
冬に2人一緒にお風呂に入れる
こんな時はどうすれば?と
当時 私も色々と疑問に思っていました。
その疑問も含め
よくある質問としてまとめてみたので
ぜひ参考にしてみて下さい。
お風呂のタイミングがずれたときの対応
兄弟で眠気や
機嫌のタイミングが合わない日は
無理に同時に
入浴させようとしなくても大丈夫です。
赤ちゃんが寝ている間に
上の子と先に入る
あるいは逆に
上の子が遊んでいる間に
赤ちゃんだけ先に入れるなど
分割スタイルで対応する方が
むしろスムーズなこともあります。
ただし 上の子を遊ばせている時は
ママの目が届くように
脱衣所などにいさせて下さいね。
毎日同じ流れにこだわらず
子どもの様子に合わせて
柔軟に動くことで
ママ・パパのストレスも減らせます。
兄弟げんかやおもちゃの取り合い対策
ケンカや
おもちゃの取り合いが起きると
せっかくの入浴時間が
バタバタしてしまいますよね。
そんなときは
「今日は○○くんが先に使って
明日は○○ちゃんね」と
順番ルールを事前に伝えておくと
子どもたちも納得しやすくなります。
おもちゃはできれば
2人分用意しておくと
取り合いを防げて安心です。
兄弟それぞれの
“お気に入り”を見つけておくと
争いも減って
入浴が穏やかな時間になります。
ちなみに我が家では
「お風呂は滑って危ないから
ケンカはしない場所」
というルールを作り
言い聞かせてみたところ
意外と守ってくれていました。
インターホン・電話対応の工夫
基本的には無視してOKですが
どうしても対応が必要な場合は
赤ちゃんをベビーチェアに
安全に座らせ
上の子には
「ママすぐ戻るからね」と伝えて
湯船から出し
風呂床で待ってもらいましょう。
目を離す時間は最小限にして
浴室の扉を開け
お風呂の声や音が
聞こえるようにしておく事が大切です。
自分の髪を乾かす時間がないとき
自分の髪は後回しになりがちですが
濡れたままだと風邪や
頭皮トラブルの原因になります。
どうしても時間が取れないときは
バスローブや吸水速乾タオルで
一時的に水分をしっかり吸い取り
子どもを寝かしつけたあとに
乾かすのがおすすめです。
ヘアドライ手袋や
タオルキャップを使うと
さらに時短になります。
上の子がお風呂を嫌がるとき
「先に遊んでから」
「テレビを見終わってから」など
お風呂に入る時間を
引き延ばすことってありますよね。
そんな場合は
「入浴後のご褒美(絵本・シールなど)」を
決めておくと切り替えやすくなります。
また
「ママと一緒におもちゃを洗おう」など
“役割”を与えると
自発的に動いてくれやすくなります。
脱衣所に暖房器具を置けない場合の工夫
暖房器具を置く事が
難しい住宅環境の場合は
・お風呂のドアを少し開けて
浴室暖房や蒸気を利用する
・お湯をはった浴槽のフタを少し開けて
蒸気で脱衣所を暖める
・カーペットやジョイントマットを敷いて
足元の冷えを軽減する
といった工夫が役立ちます。
赤ちゃんが湯船でうんちをしてしまったら?
赤ちゃんが
入浴中にうんちをしてしまうこと
ありますよね。
私の娘が1歳半くらいの頃
湯船の中にしてしまった事があります。
そんなときは慌てず
赤ちゃんと上の子を湯船から出し
シャワーで
しっかり洗い直してあげましょう。
2人にバスローブを着せて
待機させます。
上の子には
「ちょっとお風呂洗うから待っててね」
と声をかけて
安心させてあげるのがポイントです。
すぐに湯船の排水をしてしまうと
詰まってしまう可能性があるため
取れるものはすくって
ビニール袋などに入れます。
その後 排水をして
浴槽をきれいにします。
まとめ|冬のワンオペお風呂は段取りと工夫でラクになる
冬のワンオペお風呂は
育児の中でもとびきりハードな時間。
寒さや時間の制約 子どもの機嫌
自分のケアの後回し…
全部重なると心が折れそうになりますよね。
でも ちょっとした
段取りや便利アイテム
声かけの工夫で
「ラクになる瞬間」はちゃんとあります。
完璧じゃなくても大丈夫。
泣いても 順番が変わってもOK。
うまくいかない日もあるけど
なんとかなる
そう思えるだけで
少し心が軽くなるはずです。
今日のお風呂時間が
少しでも穏やかになりますように。
参考文献・引用元リスト
厚生労働省「乳幼児の健康管理と入浴指導」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
日本小児科学会「乳幼児の入浴と皮膚ケアに関するガイドライン」 https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=123
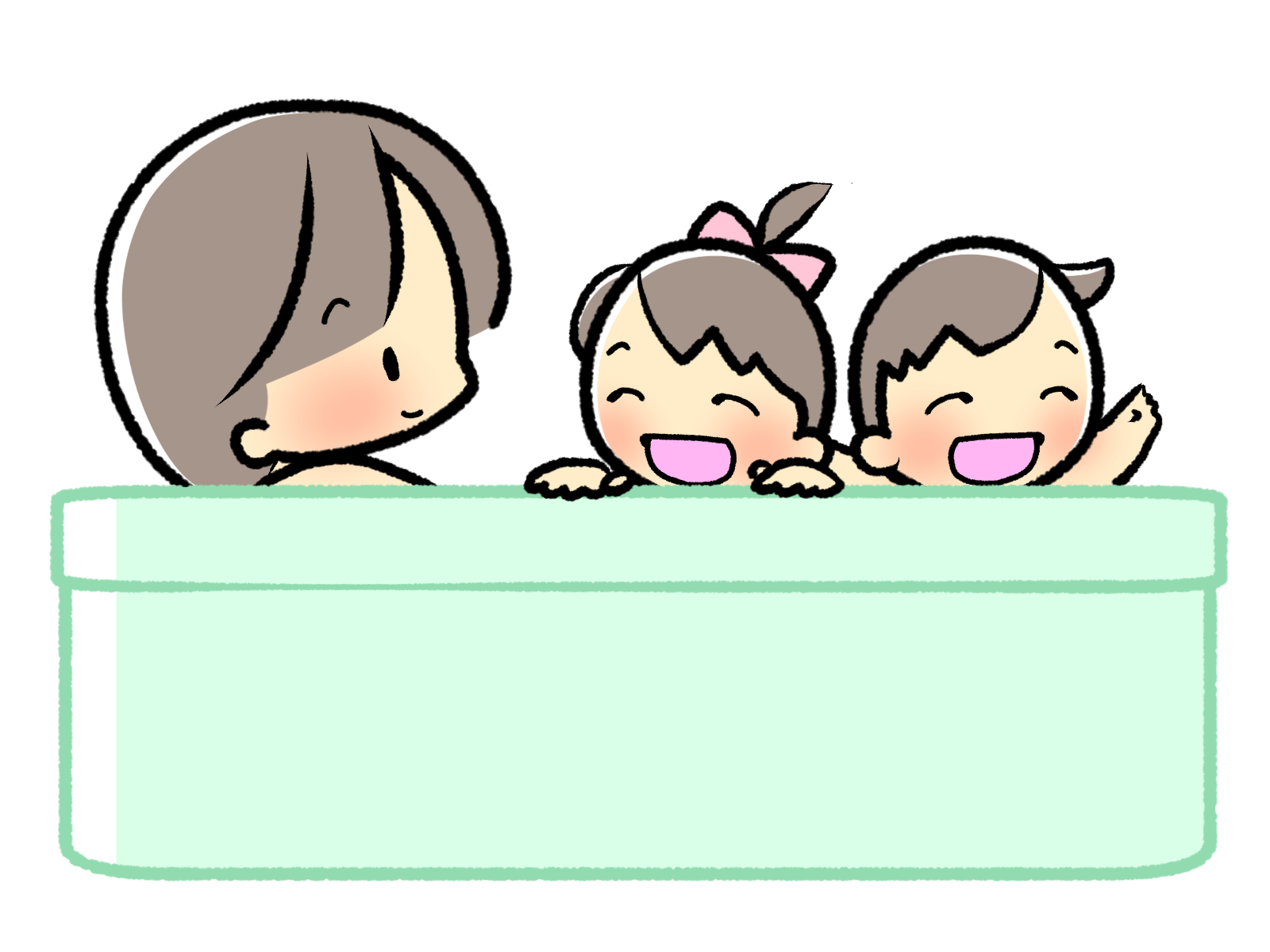


コメント