今日も一日 お仕事と育児 本当にお疲れ様です。
夕飯の準備 お風呂 そして 待ちに待った寝かしつけ。
やっと自分時間ができる!と思っても
なぜか子どもは「眠くない!」と大はしゃぎ…。
抱っこしても トントンしても なかなか寝てくれなくて
心も体もクタクタになりますよね。
そんな時 ふと
「寝かしつけには絵本が良い」と耳にするけれど
「言葉もわからない赤ちゃんに 本当に意味があるのかな?」
「そもそも いつから絵本を読めばいいの?」
と疑問に感じたことはありませんか?
安心してください。
実は 絵本の読み聞かせは
赤ちゃんが言葉を理解する前から始めることができ
子育てを少し楽にする素敵なツールになり得ます。
このサイトでは
毎日の生活に追われているママやパパのために
寝かしつけ絵本をいつから始められるのか
そしてどんな絵本を どう読めば効果的なのかを
わかりやすく解説していきます。
毎日続く寝かしつけの時間が 少しでもスムーズになって
自分の時間を取り戻せるように。
そして お子さんとの
大切なコミュニケーションの時間になるように
具体的なヒントを詰め込みました。
最後まで読んで
ぜひ今日から実践してみてください。
きっと 今までとは違う 穏やかな夜が訪れるはずです。
部屋をほんのり優しく照らすナイトライト。
絵本タイムから入眠まで自然に誘導できます。
【生後0ヶ月〜】寝かしつけ絵本はいつから始めるべき?
夜の寝かしつけを少しでも楽にしたいけれど
「絵本を読んでも効果があるのかな?」
「そもそもいつから読み聞かせを始めればいいんだろう?」
と悩んでいませんか?
「まだ言葉がわからない赤ちゃんに絵本を読んでも意味がないかも…」と
つい考えてしまいますよね。
でも 安心してください。
赤ちゃんは言葉の意味を理解していなくても
絵本を通じてママやパパからの温かい愛情をたっぷりと感じ取っています。
ここからは
寝かしつけに絵本を始めるベストなタイミングと
その素晴らしいメリットについて詳しくお伝えします。
寝かしつけ絵本を始める時期と期待できる効果
「寝かしつけに絵本」と聞くと まず気になるのが
「いつから始められるか」というタイミングですよね。
結論から言うと
絵本の読み聞かせは生後0ヶ月からでも始めることが可能です。
まだ視力が未発達な新生児期ですが
聴覚はとても敏感で
ママやパパの優しい声の抑揚やリズムを心地よく感じ
安心感を覚えることができます。
この安心感こそが
寝かしつけにおける最初の大きな効果と言えるでしょう。
生後2〜3ヶ月頃になると 少しずつ視力が発達し
絵本のコントラストがはっきりした色や
単純な形に興味を示すことがあります。
この時期は 色や形の認識を促し
視覚的な刺激を与えることで
脳の発達をサポートすることが期待できます。
生後6ヶ月以降になると 指差しをしたり
絵本に手を伸ばしたりと
絵本に積極的に関わる様子が
見られるようになるお子さんもいます。
言葉の意味を完全に理解できなくても
絵と音を関連付けて楽しむことで 集中力を育むことや
語彙力・表現力の基礎を養うことにつながるでしょう。
さらに 毎日のルーティンとして寝る前に絵本を読むことで
「この絵本が終わったら もうおやすみの時間だね」という
睡眠儀式(ねんねルーティン)を確立できる可能性が高まります。
これにより 子どもの体内時計が整い
自然と眠りにつく習慣が身につくことが期待できます。
(出典:厚生労働省「乳幼児の睡眠に関する提言」(2012年)より一部抜粋)
買って失敗したくない…そんなママにぴったり。
月額制で絵本を試し放題!
子どもの『これ大好き!』が見つかります。
![]()
寝かしつけ絵本の上手な選び方
「寝かしつけに絵本が良いのはわかったけど
書店に行くとたくさんありすぎて
どれを選んだらいいのかわからない…」
そんなふうに感じていませんか?
実は お子さんの成長に合わせた絵本を選ぶことが
寝かしつけをスムーズにする大切なポイントになります。
ここからは お子さんの年齢に合わせた選び方のヒントと
さらに効果を高めるためのコツをお伝えします。
年齢別の選び方とおすすめ絵本
お子さんの成長に合わせて絵本を選ぶことで
より楽しく 効果的に寝かしつけができるでしょう。
ここでは 月齢別に
具体的な選び方のポイントとおすすめのジャンルを紹介します。
【0歳(新生児〜1歳)】
この時期は まだ言葉の意味がわからないため
「心地よい音」と「視覚的な刺激」を重視して選ぶのが良いでしょう。
おすすめは 言葉のリズムや響きが心地よい
擬音語や擬態語が中心の絵本です。
「ばあ!」や「ごっつんこ」といった 親子で楽しめる絵本は
読み聞かせが苦手なパパでも気軽に始められます。
また 黒 白 赤などの
コントラストがはっきりした「赤ちゃん向けの絵本」は
赤ちゃんの興味を引き
視覚の発達を促すことが期待できます。
破れにくいボードブックや布絵本もおすすめです。
【1歳〜2歳】
この時期は 簡単な言葉を話し始め好奇心が旺盛になります。
「物語の導入」や
「親子のコミュニケーション」が生まれる絵本を選んでみましょう。
おすすめは 動物や食べ物など
身近なものが登場する絵本です。
「わんわん どれかな?」と問いかけたり
「一緒に探してみよう」と声をかけることで
絵本を通じて親子の温かい会話を楽しむことができるでしょう。
【2歳〜3歳】
言葉がより豊かになり
簡単な物語を理解できるようになります。
「登場人物への感情移入」や「共感」がテーマの絵本を選ぶと
子どもの想像力が育まれることが期待できます。
おすすめは 子どもの生活習慣
歯磨き 着替え トイレなどをテーマにした絵本です。
物語を通して
「僕も(私も)この子みたいに頑張ってみよう!」
という気持ちが芽生えるかもしれません。
また 寝る前の習慣を取り入れた
「おやすみ」がテーマの絵本も
入眠を促すのに役立つでしょう。
選び方のコツ|子どもの「大好き!」を見つける絵本探し
年齢別の選び方に加えて
さらに効果的な絵本選びのコツをお伝えします。
最も大切なのは
「子どもが本当に興味を持つ絵本」を見つけることです。
親が「寝かしつけに良い」と思って選んだ絵本でも
子どもが気に入らなければ なかなか絵本タイムが続きませんよね。
子どもの「好き」を尊重する
もしお子さんが電車や動物 車など
特定のテーマに夢中になっているなら
まずはそのテーマに沿った絵本を探してみましょう。
興味のあるものだと
自然と集中して読み聞かせに耳を傾けてくれます。
実際に書店や図書館で体験する
書店や図書館で
お子さんと一緒に絵本を手に取ってみるのも良い方法です。
子どもがどの絵本に一番目を輝かせるか
反応を観察してみましょう。
ママやパパが「読みたい」と思える絵本を選ぶ
読み聞かせがストレスにならないよう
ママやパパが読んでいて
楽しいと感じる絵本を選ぶことも大切です。
複雑なストーリーや早口言葉が多い絵本は
読み聞かせが負担になってしまうこともあります。
無理なく楽しく続けられる
シンプルで読みやすい文章の絵本を選ぶと良いでしょう。
月齢ごとにおすすめの絵本ジャンルを比較表にまとめました。
購入リンクもあるので、気になる絵本をすぐにチェックできます。
| 月齢 | ジャンル | 特徴・効果 | 人気の絵本はこちら |
|---|---|---|---|
| 0~1歳 | ・高コントラスト(白黒)絵本 ・擬音語・響き重視絵本 ・布絵本/ボードブック |
・視覚の発達を刺激 ・声のリズムで安心感を提供 ・丈夫で扱いやすい |
じゃあじゃあびりびり わんわん わんわん だっだぁー |
| 1~2歳 | ・動物・食べ物など身近なモチーフ ・しかけ絵本(めくる・触れる) ・言葉遊び絵本 |
・語彙力・好奇心を育む ・親子の対話が自然に生まれる |
おつきさまこんばんは どんどこ ももんちゃん コロちゃんはどこ? |
| 2~3歳 | ・簡単ストーリー絵本 ・生活習慣(歯磨き・着替え・トイレ) ・「おやすみ」絵本 |
・物語理解や共感力が高まる ・生活習慣の自立をサポート ・寝かしつけルーティンづくりに効果的 |
きんぎょがにげた いやだいやだ おやすみなさい |
絵本選びはお子さんの発達に合わせて柔軟に。
ここで紹介したジャンル以外にも
好きなテーマを優先して大丈夫です。
寝かしつけ絵本の効果的な読み方|子どもの集中力を引き出すコツ
「一生懸命読んでるのに 子どもが全然聞いてくれない…」
そんな経験はありませんか?
せっかく寝かしつけに絵本を取り入れても
子どもが集中してくれなければ
その効果も半減してしまいますよね。
実は 絵本の内容だけでなく
「読み方」にもいくつかコツがあります。
こちらでは 子どもが絵本の世界に引き込まれ
自然と眠りにつくための ちょっとした工夫をご紹介します。
寝かしつけ絵本の読み聞かせを成功させる3つのポイント
寝かしつけ絵本を成功させるには
読むタイミングと環境 そして読み方の工夫が大切です。
ここでは
今日からすぐに実践できる3つのポイントをご紹介します。
寝かしつけのルーティンにする
毎日同じ時間 同じ場所で
絵本を読むことを習慣にしてみましょう。
例えば
「お風呂に入って パジャマに着替えたら ベッドで絵本を読む」という
決まった流れを確立します。
これにより 子どもは絵本を読むことが
「もうすぐ寝る時間だ」というサインだと認識し
安心して眠りにつく準備ができるでしょう。
読み聞かせの環境を整える
寝かしつけの読み聞かせは
落ち着いた環境で行うのが理想的です。
部屋の照明を少し暗くしたり
テレビやスマートフォンの音を消したりして
静かな空間を作りましょう。
この薄暗い環境は 子どもの気持ちを落ち着かせ
眠気を誘うのに効果的かもしれません。
また 抱っこしたり 隣に座ったりと
親子のスキンシップを取りながら読むことで
子どもはより安心感を得ることができます。
読み方を工夫する
読み聞かせの最大のポイントは
「子どもの眠気を誘う優しいトーンで読む」ことです。
日中の読み聞かせのように
大げさな声色や身振り手振りは必要ありません。
優しいトーンで ゆっくりと 語りかけるように読みましょう。
また 途中で子どもが絵を指差したり 質問をしてきたりしたら
そこで一旦止まって子どもの反応に寄り添ってあげましょう。
「これはなにかな?」と聞き返したり
「そうだね ゾウさんだね」と答えることで
絵本を通じた温かいコミュニケーションが生まれます。
寝かしつけに絵本を利用した先輩ママ・パパの体験談
毎晩の寝かしつけが大変!と思うのは
たくさんのママ・パパ共通の悩みです。
そこで 先輩ママ・パパさんたちが
どのように 寝かしつけに絵本を取り入れているのか
体験談をご紹介します。
体験談 眠るのを嫌がっていた子が・・・
以前 子どもの寝かしつけに苦労していた知人(30代女性)が
毎晩「おやすみ」をテーマにした絵本を優しい声で
読み聞かせ始めたところ
それまで寝るのを嫌がっていた子どもが
絵本が終わると自ら目を閉じるようになったそうです。
もちろん これはあくまで個人の感想であり
すべてのお子さんに同じ効果があることを保証するものではありません。
体験談 寝付かずに悩んでいましたが・・・
我が家では 毎日違う絵本を読んでいましたが
子どもがなかなか寝付かずに悩んでいました。
そこで 特定の寝かしつけ絵本を2〜3冊に絞り
「この絵本を読んだら寝る時間」というルールを決めたんです。
すると 驚くほどスムーズに寝てくれるようになりました。
子どもは「いつもの絵本」を読むことで
安心して眠りにつく準備ができるのかもしれません。
体験談 絵本を諦めていました
あるママ友は 「子どもが眠そうにしてないから」と
寝かしつけ絵本を諦めていました。
でも 試しに「おやすみ」がテーマの
シンプルな絵本を読み始めたところ
最初は走り回っていたのに
読み終わる頃には静かにベッドに横になってくれたそうです。
絵本の持つ 心を落ち着かせる力ってすごいですよね。
体験談 読み聞かせが苦手で・・・
我が家のパパは 絵本の読み聞かせが少し苦手で
いつも私が担当していました。
でも ある日「今日は俺が読んでみる」と言って
優しい声でゆっくりと絵本を読んでくれたんです。
すると いつもより早く寝てくれて
子どももパパの読み聞かせを気に入ったみたい。
それ以来 寝かしつけはパパの担当になり
私の貴重な「自分時間」が増えました。
FAQ 回答
初めて 寝かしつけに絵本を取り入れようと思うとき
様々な疑問が出てくると思います。
よくある質問をまとめてみたので
ぜひ 参考にしてみて下さい。
寝かしつけ絵本は毎日読んだほうがいいですか?
毎日読むことをおすすめします。
寝かしつけ絵本を毎日の習慣にすることで
「絵本を読む=もうすぐ寝る時間」という睡眠儀式が確立され
子どもの体内時計が整いやすくなる可能性があります。
これにより 入眠がスムーズになることが期待できるでしょう。
もちろん 毎日完璧を目指す必要はありません。
疲れている日や忙しい日は無理をせず
できる日だけでも続けることが大切です。
できる範囲で続けることで
親子にとってかけがえのない大切な時間になるでしょう。
読み聞かせの途中で子どもが飽きてしまったらどうすればいいですか?
無理に最後まで読もうとしなくても大丈夫です。
子どもが飽きて絵本から注意がそれてしまったら
一度読み聞かせを中断してもいいでしょう。
子どもの関心が他に移ってしまったときは
無理に引き止めようとせず
「今日はもうおしまいかな?」と優しく声をかけてあげましょう。
読み聞かせは 親子の楽しい時間であるべきです。
無理やり読まされると感じてしまうと
絵本そのものを嫌いになってしまう可能性もあります。
もし読み聞かせの途中で子どもが寝てしまったら
静かに絵本を閉じてあげましょう。
どんな種類の絵本が寝かしつけに向いていますか?
寝かしつけには 静かで落ち着いた内容の絵本が向いています。
例えば 登場人物が眠りにつくストーリーの絵本や
動物たちが眠る様子を描いた絵本
優しい色のイラストで構成された絵本などがおすすめです。
また 擬音語や擬態語の響きが心地よい絵本も
入眠を促す効果が期待できるでしょう。
逆に 興奮を誘うようなアップテンポなストーリーや
賑やかな絵本は 日中の読み聞かせ向きと言えるかもしれません。
寝かしつけ絵本は 何冊くらい用意すればいいですか?
たくさんの絵本を用意する必要はありません。
お気に入りの絵本を数冊用意しておくだけで十分です。
子どもは 同じ絵本を繰り返し読むことを好む傾向があります。
毎回同じ絵本を読むことで ストーリーを覚え
絵本の世界に安心して入ることができます。
また 季節やイベントに合わせた絵本を数冊加えて
変化を楽しむのも良い方法です。
無理のない範囲で お子さんが
「これ 大好き!」と思える絵本を見つけてあげましょう。
読み聞かせの時間がなかなかとれません。どうすればいいですか?
共働きで忙しい日々の中
まとまった時間をとるのは難しいですよね。
そんな時は 「毎日3分だけ」と決めてみましょう。
たった3分でも 毎日続けることが大切です。
寝る前の歯磨きの後や パジャマに着替えた後など
決まったルーティンの中に組み込むことで 習慣化しやすくなります。
また パパとママで分担するのもおすすめです。
「今日はパパが読む日」「明日はママが読む日」と決めることで
無理なく続けることができます。
小さな頃から世界と触れ合う事ができる
世界の絵本を毎月届けてくれるサブスク
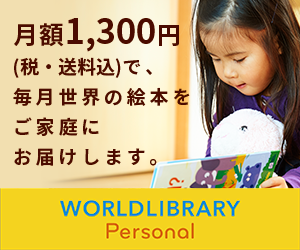
まとめ
夜の寝かしつけに絵本をいつから始めるか
そしてその効果的な方法についてご紹介しました。
絵本の読み聞かせは 生後0ヶ月からでも始められ
子どもの心の安定や睡眠習慣の確立に役立つことが
お分かりいただけたかと思います。
一番大切なのは
完璧な読み聞かせを目指すことではなく
お子さんとのスキンシップを楽しみ
絵本を通じてコミュニケーションをとることです。
まずは お子さんが「これ 読んで!」と
興味を持ちそうな絵本を
1冊手に取ってみることから始めてみませんか?
毎日忙しいママやパパも 絵本を味方につけることで
寝かしつけの時間が少しでも楽になり
自分時間を確保できるかもしれません。
お子さんとの大切な絵本タイムが
日々の疲れを癒してくれる特別な時間になることを願っています。
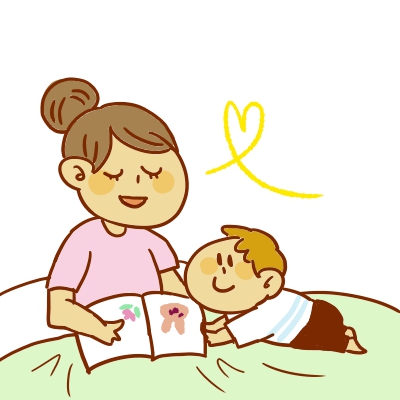


コメント